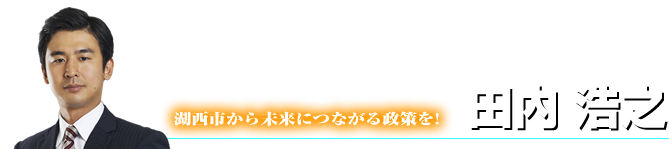この度11月の市長選挙に立候補することを決断いたしました。
湖西市のために働くには県議か市長かどちらの立場がよいのか悩みましたが、交通や医療などの市の課題に直接関わるため、市長選挙への立候補を決めました。
9月6日に記者会見を行い、市長に当選できたら取り組みたいことを述べさせていただきました。
公約は以下の通りですが、具体的な内容は記者会見の発言内容を掲載致しますので是非ご覧ください。
公約
基本理念
魅力的な湖西市を子どもたちへ
重点政策
01命を守る
☆地震・津波、豪雨対策の推進
☆湖西病院経営改革と地域医療の充実
02湖西市を暮らしやすく
☆行きたいときに市内どこでもいける公共交通の実現
☆湖西中学校区、白須賀中学校区の活性化
☆魅力的な商業地域の創出と景観整備
☆自然環境の保全と利活用
☆文化・芸術の振興
03 湖西市を元気にする
☆製造業への支援
☆水産資源の確保と農業振興
☆障がい者雇用の促進と就労施設への支援
☆観光振興
☆新規創業支援、企業誘致
04学びと子育ての環境を整える
☆自然を生かした体験学習の充実
☆教員の職場環境改善とAI技術活用による個々に適した教育の提供
☆屋外屋内子どもの遊び場の充実
☆入所待ち児童解消
記者会見
本日は私田内浩之の記者会見にお越しいただき誠にありがとうございます。
この度、11月に行われる湖西市長選挙に立候補することを決意いたしました。
私は地元湖西市をより良くしたい、子どもたちが大人になった時に「住み続けたいな」と思える湖西市にしたいと、議員を目指しました。約14年間湖西市選出の県議会議員をつとめ地元の発展に力を注げたことは、市民のみなさまのお支えがあってのことであり、心より感謝申し上げます。湖西市のために働くには県議を続けるべきか市長選に出るべきか悩みましたが、市の課題に直接関わり、よりよい湖西市を市民のみなさまとともに目指すことにいたしました。
本日は私が市長になったら取り組みたいことをお話したいと思います。
01命を守る
私が県議会議員選挙にはじめて挑戦した時も政治は命を守ることと訴え、今でも考え方は変わりません。そのように考えるのは、私の初選挙は東日本大震災の直後であり、地元のためにやらなければいけないことはまず地震津波対策だと考えたからです。また、当選後訪問した岩手県山田町の職員さんが泣きながら「私の町では多くの死者が出てしまった、あなたのまちでは同じことがないように頑張ってほしい」と言われましたので、政治は命を守ることだという思いはますます強くなりました。
具体的な内容は
☆地震・津波、豪雨対策の推進についてですが、実態に即した福祉避難所の設置運用、仮設住宅の不足への対応、避難所のエアコン設置他環境整備、実態に即した避難訓練の実施、避難者安否確認登録システムの構築などの課題に、取り組みたいと考えています。湖西市の現在の危機管理官はとても頼りになりますので心強い限りです。また、日頃市民の皆様のために頑張ってくださっている消防に関しても、消防長は素晴らしい方ですし、隊員の方も素晴らしい方ばかりです。当選後に消防の皆さんとご相談の上、足りない機材や環境整備に努めたいと考えています。また消防団への支援についても取り組みます。
そして、県議としても長年取り組んできた緊急輸送路の確保や、河川工事、土砂災害危険個所の対策、急傾斜地対策、有事と平時の職員数調整広域支援などにも引き続き県と連携して取り組みます。
☆湖西病院経営改革と地域医療の充実についてですが、病院を利用する私の支援者からは湖西病院は働いている人も親切で良い病院だと伺っています。しかし、一般会計からの繰り入れが多いのも事実ですので、民間企業にいた経験も活かし、経営改革を医師や看護師の皆さんと一緒に取り組みたいと考えています。具体的には、外来人数の増加、小児科・脳神経外科医師の招へい、間接部門の合理化を行ったうえで収入を増やし、現在60近い職員給与比率を50%以内にもっていきたいと考えています。
02湖西市を暮らしやすく
市民の皆様の満足度の向上をはかる政策を実行したいと考えています。湖西市の市民意識調査では、住みやすい理由として自然環境が豊か、地元が好き、働く場所が充実しているなどがあげられる一方、住みにくい理由としては交通の便が良くないことがあげられています。特に車を運転できない高齢者や子ども達、障がい者のみなさまが住みにくい状況にあります。また、医療サービスが充実していない、買い物や外食が不便なことが住みにくい理由として挙げられています。私はこの住みにくい理由に挙げられている分野に行政の資源を投入し民間の力もお借りして、市民のみなさまが健康であり市民満足度の高い地域を目指します。
☆行きたいときに市内どこでもいける公共交通の実現についてですが、交通に関してはゼロベースで考え、市内にデマンド交通を張り巡らせ、市内であれば行きたいときにどこでもいける環境をつくります。高齢者や子どもたち、障がい者の方が大雨に打たれながらバスを待つ、交通機関がないので長時間歩く状況をなくします。
☆湖西中学校区、白須賀中学校区の活性化についてですが、徹底的に空き家対策を講じたうえで、既存集落においての宅地の供給に取り組み、人口増加施策を展開したいと考えています。具体的には都市計画法34条を使い、加古川市田園まちづくり計画制度のような制度をつくりたいです。
☆魅力的な商業地域の創出と景観整備についてですが、小さな経済活動の活発化、つまり個店の魅力発信や新規個店の開業に力を注ぎます。また駅、関所周辺を小さな民間投資が生まれる公共不動産活用の切り口で賑やかにしたいです。例えば使える公共用地に駅前待合所をつくったり、スペースに椅子や机を置いて市民の皆様に使っていただいたり、区画に区切って民間に貸出したりしたいです。また景観整備に関しても旧新居町の施策を見習い道路や公共スペースの緑化に取り組みたいですし、山間部や海岸部の景観を阻害する太陽光発電のような開発を抑制する施策を実施したいと考えています。そのためには旧湖西市の景観計画を作成することが必要だと考えています。
☆自然環境の保全と利活用についてですが、湖西連峰、白須賀海岸をはじめとする浜名湖県立自然公園の保全と利活用を進めたいと思います。まず湖西連峰については登山道整備や美しい森づくり、 大知波親水公園や梅田親水公園の整備を地域の皆さまと協力してすすめたいと思います。また、白須賀海岸に関しては地域のNPO法人等と協力してサーフスポットの整備(駐車場の拡張、ビーチハウス整備)やサーフタウンらしい景観づくりに取り組みたいです。また、環境保全の意識醸成の観点からも古着のリサイクルにも市として取り組みたいと思います。
☆文化・芸術振興についてですが、アートスペースの設置、図書館の芸術文化図書の充実、県アーツカウンシルと連携した市民文化活動の支援を通して、市民の皆さまが芸術に触れあう機会を増やし、市民の皆様の文化芸術活動を後押ししていきます。
03 湖西市を元気にする
☆製造業への支援についてですが、県議としても相当力をいれてまいりましたが、引き続き国県の支援策との連携、大倉度茶屋松線他等都市計画道路の整備、工業用地の供給、大企業中小マッチング等に取り組みます。
☆水産資源の確保と農業振興についてですが、まず水産業ですが浜名湖の環境改善(森づくり含む)と資源確保・海業、つまり漁師の皆さまが漁業以外の事業展開で収入を確保することに取り組みます。また、農業においては県議としてJAとぴあ浜松の青壮年部湖西支部の皆さまと連携をとりスマート農業化支援やそれに適した農地づくりを進めてまいりました。引き続きこれらに取り組むとともに、商業や観光とのとの異業種連携を進めて地元のみなさまに湖西の産物の良さを知っていただくとともに、売価の向上を目指します。
☆障がい者雇用の促進と就労施設への支援については、各施設の経営が安定するように、民間の皆さまと連携し、販路の開拓や商品開発、仕事の創出に取り組みます。
☆観光振興については課題が何点かあると考えています。
統一したイメージづくりを伴う観光マーケティング・プロモーションやセグメンテーション ターゲティング ポジショニング STP を意識した体験型観光(食、関所周辺、アクティビティ (サイクリング トレッキング サーフィン マリン(釣り))の商品造成。
また、高価格帯のホテル誘致や奥浜名湖地区との連携、インバウンド受け入れ態勢の構築などの課題があると考えていますのでこれらの課題に観光協会 商工会 湖西市一体で取り組みたいと考えています。
☆新規創業支援 企業誘致
・スモールビジネスの開業支援については商工会さんで一生懸命とりくんでいただいていますので、市としては開業する場の提供に取り組みたいです。また、企業誘致に関しては、県議時代も取り組み、実績を積んできた自負もありますが、人口流出が激しい女性が好む仕事、先ほどの高級ホテルもそうですが、ファッション・デザイン系の会社の誘致に取り組みます。
04学びと子育ての環境を整える
教育や産業などの重要な分野で時代の移り変わりは大変激しく、今まで以上に柔軟に変化し、挑戦することが求められています。子どもたちには豊かな自然を通して体験し、感じ、考え、やってみることで創造性とチャレンジ精神を育んでもらいたいと考えています。
☆自然を生かした体験学習の充実
都会のインターナショナルスクールではわざわざ高いお金をはらって地方に出向き、海や山での自然体験を行っています。湖西市には海、湖、山全てあります。私も浜名湖で友達と釣りをしたり、あさりを獲ったり、山ではターザンロープを自作して遊んだり楽しい思い出がたくさんありますが、今の子どもたちはそうした体験が少なくなっていると感じます。また、個々の学校でやっていただいている農業、漁業の体験も市内の学校に広げ、体験する→感じる→考える→やってみる 体験をすることで創造性を育んでいただきたいと考えています。
☆教員の職場環境改善とAI技術活用等による個々に適した教育の提供についてですが、AI型の教材、つまり児童・生徒一人ひとりの習熟度に合わせて最適な問題を出題するアダプティブラーニング教材の導入を現場の先生方と一緒に検討したいと思います。学校の先生方の多忙化は大きな問題です。それにより、生徒が先生と向き合う時間が減ってしまっています。昔は、昼休みの時間に先生と遊んだ記憶が皆さんあるのではないでしょうか。私も県議としてスクールサポートスタッフの導入などに取り組んでまいりましたが、一部の学習をAI教材に任せることで子供たちの学力向上と教員の職場環境改善を目指します。
☆屋外屋内子どもの遊び場の充実 運動公園、湖西連峰、海岸他
☆入所待ち児童解消
政策の中身については以上です。これらの政策を10年の民間経験、14年間県議会議員として培ってきた県とのパイプと民間企業との人脈、そして市民のみなさまのお声を伺い課題解決してきた経験を生かし、市の職員の皆さん、市民のみなさんと一緒に実行していきたいと考えます。