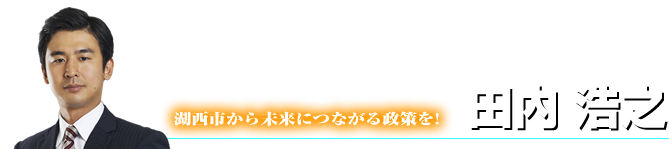県議会平成25年12月議会総務委員会のご報告
私たち県議会議員は、本会議の他に7つの常任委員会に分かれて議論します。
その場で私たち議員は、県職員の方々に質問や要望というかたちで、議員が求められている行政に対する監視・提案をしていきます。私は、平成25年度において防災や県の財政政策を担う総務委員会において副委員長を仰せつかっています。以下に、私の質問(抜粋)と県の回答を掲載いたします。
危機管理部関係
①緊急輸送路の液状化対策について
Q 緊急輸送路の液状化対策を今後どの様に進めていくのか、しっかりボーリング調査などをやって対策を講じていくのか伺う。併せて、250mメッシュ単位の液状化マップはまだホームページ上にはなかったと思うが、データがあるのか、公表する予定があるのかどうか伺う。
A 緊急輸送路の対策については、地震・津波対策アクションプログラム2013に基づき交通基盤部が中心となって道路管理者が必要な対策を講じる計画になっている。今回の第二次報告の中で、緊急輸送路の液状化による通行支障の発生の可能性について評価をしているが、その方法は、第一次報告の中で設定した液状化の危険度を活用し、液状化の危険度が大きいところを通過している道路については、液状化による被害を受けるおそれがある。影響度ランク「B」、小被害が発生する可能性があるということで、当日中から3日間程度の間に緊急輸送が可能になると見込んでいる。具体的に、それぞれの道路のボーリングデータなどを基に個別の診断をしている訳ではなく、緊急輸送路が通過している250mメッシュの液状化危険度の判定結果に基づいて道路の影響度ランクを想定している。
液状化マップについては、250mメッシュで液状化の危険度の評価したデータは、すべて県で所持している。現在、静岡県の統合基盤地理情報システムに震度分布と津波の浸水想定を掲載しており、インターネットで御覧いただけるようにしているが、次の段階でどういう情報を掲載するかを検討しているところであり、液状化のマップも、その候補の1つとなっている。県民の皆様の防災対策にとって重要な情報は、県の統合基盤地理情報システムに掲載して、積極的に公表していきたいと考えている。
②土砂災害避難勧告・指示に対しての県の支援強化について
Q 伊豆大島の土砂災害を受けた静岡新聞の県内首長へのアンケートにもあったが、今後県で市の避難勧告・指示に対して支援を強化していく予定はあるか。
A 従前より、県としては、指定された大きな河川については、河川に観測地点をいくつか設け、降雨時の雨量・水位や設計上の流量に対してどれだけの危険水位になっているかなどの情報をリアルタイムで提供しており、これは一般県民の方にはインターネットの「サイポスレーダー」で見ることができる。また、土砂災害についても、雨が降り土壌が雨を含めば山は崩れやすくなるので、それらを指数化して、地図上のメッシュ・データとして市町へ提供し、これもインターネットでも公開している。警報発表時には、市町と県の危機管理部、交通基盤部の職員が待機しており、雨量の状況や、さらに気象台からは気象予測情報を随時交換し、市町へ伝えている。市町では、夜間などでは避難勧告を躊躇する場合もあるので、科学的根拠により、どこの時点で避難勧告を出すのか県や気象台のデータを申し添えて、市町の皆さんの背中を押せるような体制を組んで取り組んでいる。また、渇水期であるこの時期に、風水害を勉強する機会として、この19日に県内全市町を集め、システムの詳細や運用方法などについての研修を行う予定である。
Q 背中を押すというのは、そろそろ出したほうがいいですよと助言するということでよいか。
A そのとおりである。避難勧告等の発令の権限は、災害対策基本法上は市町村長にある。仮に県のデータではまだ安全であっても、現場の状況を見て危険であると判断し、発令する場合も想定して、権限は市町村長にあるものとしている。その決断ができるよう精一杯後押しをしていきたい。
③発災時の空路を使った物資の輸送について
緊急輸送路が分断されると空路に頼らざるを得ない状況になるが、各市町が空路に対する受入の訓練をしっかり実施しているか県で把握しているか。また、受け入れ側の各市町に対して、体制として整えるようマニュアルがあるとか、各市町へ投げかけなど随時行われているのか。
専用の飛行場は県内には浜松基地、静浜基地、静岡空港しかないので、各市町で空からの物資を受け入れるのは、ヘリコプターの運用ということになる。県内には災害時にヘリコプターを使うことを想定し、自衛隊の基地と県営の運動公園など5箇所を中核へリポートとして位置付け、各市町あるいは政令市では区ごとに支援を受けられるよう拠点ヘリポートを49箇所選定している。さらに、陸路が途絶し、孤立が予想される集落に対して、物資を搬送したり、怪我人を地面からピックアップすることを想定した現地へリポートとして459箇所を選定している。中核、拠点ヘリポートについては、総合防災訓練や平成19年度から実施している航空受援訓練で使用に努めている。現地へリポートについては、航空受援訓練等で実際に使ってみるということで、現在までに約3分の1にあたる153箇所について実際に離着陸して効果を確かめている。なお、そもそもヘリポートを選定するときに、事前に県の消防防災航空隊の要員や自衛隊OB、現職の自衛隊の部隊の方などに現地を立会いいただき、災害時のヘリコプターの運用に支障が無いことを確かめた上で選定し、災害に備えている。9月1日の富士宮市・富士市の総合防災訓練では、地元の受け入れ作業を常備消防と消防団に担っていただいた。彼らは災害時に実際対応する方たちであり、自衛隊OB等の指導を受け、実際にヘリコプターを下ろすときの動作の訓練を実施した。現地へリポートでは、実際に配備できるのは、消防団員やそのOBのみという状況なので、簡単な方法として、白い布やシーツを用意し、「地上に支障がないので降りても良いのであれば、旗を振ってください。そうでなければ動かないでじっとしていて下さい。」といった簡単な方法を示し、指導に努めており、航空受援訓練では毎年何箇所かこうした訓練を実施している。今後、この方法のマニュアル整備や配布に努めていく。
④発災時の県職員配置体制について
Q 発災直後と72時間経過後の県職員配置体制は変える必要があると思うが、県の体制は変わるのか。
A 震度5強以上で役割分担に基づき全職員を動員するが、災害対策本部の約260名の要員は3班にわけており、参集直後は全員で業務にあたる。夜間や休憩を入れる場合は、2班が対応し1班を残すことで、3日間は全員体制でしのぐこととし、以降は通常の日勤を主体として夜間を必要な要員でカバーすることを考えている。明確なマニュアル、ルールとしては決めていないが、参集状況などに応じて柔軟に考えていきたい。基本は72時間までは3分の2の体制、それ以降は日勤体制プラス夜間時間外の対応職員の体制をオペレーションの一環として考えている。
※時系列の中で、県全体の効果的な人員配置を検討いただきたいと要望いたしました。
経営管理部関係
①県の資産の一体的な管理・活用について
Q 県有施設の総量適正化に向けた具体的な金額目標は持っているか。
A 施設総量は、毎年の行政需要に対応していくものであり、将来にわたっての削減目標というものはない。例えば静岡南高校は自然史博物館として、長泉高校はファルマバレー関連施設にというように、その他のものに転換していくものもある。
Q 1,000㎡未満の小規模未利用地の売却も促進すべきと考えるが、進捗はどうか。
A 未利用県有地を全庁で調整する会議があり、1,000㎡以下の小規模未利用地も全てあげて、庁内での利用が無ければ、地元市町に聞いて、市町の利用が無ければ全て売却することとしている。売却困難な小さな土地や無道路地は、隣地所有者に買い受けてもらうことを進めている。
※長期の塩漬け未利用地は、不動産会社などと提携して売っていくことを考えてほしいと要望いたしました。
Q 施設の統廃合を具体化することになった場合の市町と連携をどのように考えているか。
A 公共施設を取り巻く課題は、県と市町で共通する部分が多く、県・市町が連携して取り組んでいくことが重要である。10月開催の県・政令指定都市サミットにおいて、県・市町が連携して、公共施設の情報共有を図り、公共施設の管理手法について研究する連絡会を設置することとされた。これを受けて、県と政令指定都市が中心となり、研究会を早期に設置することとし、年度内の開催に向けて現在調整しているところである。施設の統廃合は将来的な研究課題となるかもしれないが、まずは情報共有や管理手法の研究から着手したいと考えている。
②経常収支比率(どのくらい予算に余裕があるかを示すもの、%が上がれば上がるほど余裕がない)について
Q 経常収支比率が90%を上回っている中で、分子の部分、人件費等にまで手を入れて経常収支比率90%以下という目標を達成するつもりな のか。公債費、扶助費の削減は厳しいが、残業代など人件費の削減可能な部分がまだあるのではないか。
A 分子は社会保障関係経費や公債費など、なかなか減らすことができない状況にある。分母中では税が最も大きいため、現在、徴収対策の強化を図っている。ファシリティマネジメントにおける県有地の売却も分母に含まれるので、規模は小さいかもしれないが、努力している。ファシリティマネジメントのもう一方の取組である施設の維持管理経費を節減するということが分子の削減になることから、こうした取組を進めているところである。がしかし、こうした状況の下では、経常収支比率90%以下の目標達成は厳しいところがある。全体の税収が増加しないことに加え、社会保障費が増加している状況にあるため、なかなか努力が追いつかないところがあるが、経常収支比率を下げることについては、政策的に使えるお金が増えることになるため、努力を続けてまいりたい。
※残業代についての言及はなかったので次回委員会にて再度取り上げたいと思います。
③総合計画と財政の中期見通しとの関係について
Q 総合計画と財政の中期見通しとの関係はどのようになっているのか。
A 現在の基本計画の計画期間である4年間について言えば、この間の具体的な主な取組、例えば草薙運動場のリニューアルやプラサヴェルデの整備、防災無線デジタル化といった事業について、財政の中期見通しにおける歳出の試算に反映し、総合計画と中期見通しとの整合性を確保している。
※大きなハード整備だけでなく、もう少し細かく、総合計画と中期見通しを連動させてほしいと要望いたしました。
④通常債残高について
Q 通常債残高が2兆円を下回っていれば良しという県の目標の根拠は?
A 県債残高の目標については、財政危機宣言を出した平成12年度の予算編成において、県債残高が2兆円を超えようとしていた状況にあり、将来、公債費として財政負担がのしかかってくる恐れがあったことから、県債残高に一定の歯止めをかける必要があると考え、2兆円に設定したところであるが特に根拠はない。投資的経費の縮減を図るなどして、通常債の発行を抑制した結果、24年度末においては、1兆8,248億円と目標の2兆円を大幅に下回っている。・次期基本計画においては、景気動向や災害復旧への対応、地震津波対策の推進のため、一定の幅を持たせて県債残高を管理したいと考え、2兆円を上限として目標設定した。他県の状況については、目標設定はまちまちであり、全国的な基準はないところであるが、他県でも、例えば基準年度を設定し、その水準を超えないように、という目標を定めているところがいくつかある。に
※根拠ある設定金額を検討してもらうよう要望いたしました。