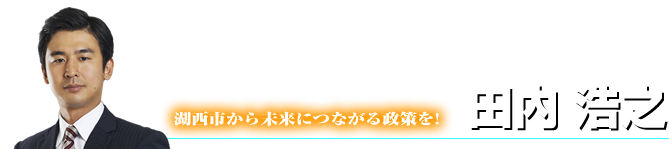9月20日静岡県議会本会議にて、ふじのくに県民クラブを代表して質問を行いました。
内容を掲載いたしますので、是非ご覧ください。
~令和元年9月静岡県議会定例会に対する質問~
質問者:田内 浩之 議員
質問日:令和元年9月20日(金)【2番目】
会派名:ふじのくに県民クラブ
項 目 1 知事の政治姿勢について
(1)人口減少の抑制に向けた総合戦略の見直し
答弁者 知事
質問要旨 人口減少社会の克服に向けて、「美しい“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき地方創生の取組を推進し、一定の成果があったと理解している。
しかしながら、東京一極集中がさらに加速し、合計特殊出生率もこの2年は低下傾向で推移しており、今後も自然減少が継続することが確実である。
国では、今後は、人口減少に適応する取組にも重点を置く方針を示している。人口減少は避けられない状況にあり、人口が減少しても快適で安全な社会を創造する「適応戦略」は重要性を増している。
しかし、「適応戦略」は、社会が安定する静止人口の将来的な実現も見据えて取り組むべきものであり、人口減少を可能な限り抑制する取組を、これまで以上に粘り強く展開していくことが必要と考えるが、今後、人口減少の抑制に向けてどのように取り組んでいくのか伺う。
<答弁内容>
田内議員にお答えいたします。私の政治姿勢についてのうち、人口減少の抑制に向けた総合戦略の見直しについてであります。
本県では、国に先駆けて「人口問題に関する有識者会議」を立ち上げました。この有識者会議からの提言を踏まえて、人口の急激な減少を抑制するとともに、避けることのできない人口減少社会への適応を図り、長期的視点で社会が安定する静止人口状態の実現を目指すべく、「美しい“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生総合戦略」をオール静岡で推進してきたところであります。
次期総合戦略におきましても、自然減対策と社会減対策から成る「人口減少のいわゆる「抑制」戦略」と、人口が減少しても快適で安全な生活の維持を目指す「人口減少社会への「適応」戦略」は、堅持すべき戦略であると考えております。二つの戦略を両面から進めることで、相乗効果の発揮につなげ、人口減少社会の克服に全力で取り組んでまるところであります。
議員御指摘の抑制戦略の強化につきましては、合計特殊出生率がこの2年間に低下傾向で推移したことを踏まえまして、県と市町で少子化の課題を共有する「ふじのくに少子化対策連携会議」を8月に立ち上げたところであります。国が次期総合戦略の主要な取組に掲げる、地域ごとの課題に対応した地域アプローチ型の少子化対策に先んじまして、県と市町が一体となった優良事業の横展開、市町間の広域連携施策の構築などを進めており、切れ目のない結婚・出産・子育て支援の充実を図ってまいります。
転出超過の主な要因は、若者が、大学進学等を契機に、主に東京圏などの県外に転出していることにあります。県外に転出した若者を対象としたアンケート調査を行い、就職時に本県へ戻らない理由としていただきました回答は、「やってみたい仕事や勤め先がない」、「給与水準の高い仕事がない」、「交通のアクセスが充分でない」、「娯楽・レジャー施設に満足できない」等々が挙がっているところです。
このため、新産業集積クラスターやCNFプロジェクト、MaOIプロジェクト、ICT産業等の次世代産業の創出や、首都圏からの本社機能の移転を進めるなど、若者にとって魅力ある雇用の場の創出に注力をいたします。また、ふじのくにパスポートあるいは若者向け移住ポータルサイトの情報の充実を図りまして、首都圏と比べて働きやすく住みやすい本県の魅力を発信いたします。そして自分らしい生き方や働き方を模索する首都圏在住の若者を呼び込んでまいります。
今後とも、本県が、地方創生の先導役を担うという強い気概を持ちまして、「生まれてよし 老いてよし」、「生んでよし 育ててよし」、「学んでよし 働いてよし」、「住んでよし 訪れてよし」の理想郷の実現に向けて、全力を傾注してまいります。
項 目 1 知事の政治姿勢について
(2)人事施策
答弁者 吉林副知事
質問要旨 最近は、1年で部長の職を解かれる職員が多く、関わった仕事をやりきれないのではないかと懸念している。部長の人事はどのような戦略に基づき考えているのか、また、東京事務所長経験者がそのまま退職することは、とてももったいなく感じるが、県の人事施策においてどのような課題を認識し対応しているのか、所見を伺う。
<答弁内容>
知事の政治姿勢についてのうち、人事施策についてお答えをいたします。
本県では、県政の重要課題に迅速かつ的確に対応できるよう、職員の採用や育成、また職員の意欲、能力、適性や経験等をきめ細かく把握し、適材適所の配置を行うなどの人事施策を進めております。
このうち人事異動におきましては、施策の継続性を考慮しつつ、それぞれの職に必要とされる高い専門性やマネジメント能力を有する者を部局長に配置をしております。一方、その結果として、部局長が在任1年で退職、転出する場合があることは、人事施策上の課題であると認識をしております。
こうしたことから、本県では、国における定年延長の議論も見据え、再任用制度を活用し定年の枠にとらわれずに適材適所の人事異動を柔軟に行っております。やむを得ず部局長の職において在任1年で定年退職や転出をする場合におきましては、後任に十分な職務経験を有する者を充てるよう、配慮をしているところでございます。
また、議員御指摘の東京事務所長など人的ネットワークの集積する職や、より高度かつ専門的な知見を備えた職にある者の退職等が見込まれる際におきましては、こうした知見等を遺漏なく継承していくことも課題であるというふうに認識しております。
こうした知見等の継承につきましては、施策の後退を招くことがないよう、平素から当該職員の事務引継のみならず、関係する全ての職員が連携して、組織全体で知見等の共有を図ることとしております。また、このような職員が定年を迎える場合におきましては、有用な知見等を引き続き県や地域において活用いただけますよう、再任用を含めた当該職員の処遇や、再就職に向けた人材情報の提供につきまして考慮をしてまいります。
今後もこうした取組に加えまして、高度な専門性を有する人材の育成に向けた若年期からのキャリア意識の醸成や、幹部ポストへの若手職員の積極的な登用など、中長期的な視点から人事施策を進めてまいります。
以上であります。
項 目 1 知事の政治姿勢について
(3)リニア中央新幹線に対する静岡県の考え方と対応
答弁者 知事
質問要旨 次に、リニア中央新幹線に対する静岡県の考え方と対応について伺います。
静岡県は命の水である大井川の水資源と南アルプスの自然環境を守るためにJR東海と科学的根拠に基づき対話を進めています。
そして、6月6日、JR東海へ中間意見書を提出し専門部会において対話を進めています。
この件に関しましてわが会派も勉強会の開催や議員間での意見交換を進めてまいりました。
この問題に対して、大井川の水量全量回復は死守すべきである、また、科学的な見地に基づき全量回復が担保され工事を進める段階に入った際、予期せぬ事由が発生し水量の減少等が発生した際には相応の補償がなされる協定を事前に結ぶべきとわが会派は主張します。
そこで、この主張に対する県の所見を伺います。
また、現在水量に焦点が当てられていますが、水質の確保と自然環境の保全もとても大切な課題です。
水質に対しては、地下に埋まっている鉱物の流出が懸念されており、また、自然環境の保全に対しては、生態系のバランスを保つうえで欠かせない生物、つまり「キーストーン種」の減少による生態系の破壊など様々な課題が山積しています。
そこで、この水質の確保と自然環境の保全という2つの課題に対しての県の所見も同時に伺います。
<答弁内容>
次に、リニア中央新幹線に対する静岡県の考え方と対応についてであります。
リニア中央新幹線のトンネル工事に伴う大井川の流量減少問題につきまして、平成26年のアセス準備書に対する意見書の段階から、終始一貫し「トンネル湧水の全量を大井川水系に戻す」ことを強く求めてまいりました。以来、5年の間まともな回答がないままに過ぎまして、昨年10月になってようやく、JR東海から「トンネル湧水の全量を大井川水系に戻す」という表明を頂いたところであります。
しかし、湧水の戻し方など具体的な対応策についての論点を整理した中間意見書に対する7月の回答案の中で、JR東海は「湧水が他県に流出する期間がある」ことを明らかにいたしまして、我々を驚かせました。今月6日に提出された回答書の中では「県境付近の湧水については、引き続き検討する」と述べられております。湧水の全量を戻すことは、約束事でございますから、JR東海はそれを可能にする技術的工法を明らかにし、責務を果たさなければなりません。
南アルプスを源流とする大井川は、長い歴史の中で、大切に受け継がれた財産であります。流域住民や利水者の皆様にとっては、生活や経済活動に欠かせない「命の水」であります。「トンネル工事に伴い流出する湧水の全量を戻すこと」に関しましては、決して譲ることなく取り組んでまいります。
議員御指摘の補償に関する取り決め等につきましては、工事でございますので、しかも相手は南アルプスでございますから、予期せぬ事態が発生する可能性は、否定できません。それゆえ、JR東海と調整いたします。
鉱物の流出に対する水質の確保につきましては、JR東海は、水質汚濁防止法に基づく排水基準による管理を考えておられます。しかし、大井川の上流は排水基準値よりもはるかに優れた清流でありますために、大井川の水質を守っていく基準としては十分ではありません。
また、自然環境の保全につきましては、JR東海の生物調査がキーストーン種を含む現状の生態系としては把握し切れておらず、南アルプスの正確な食物連鎖図も作成できておりません。このため、河川や沢の流量の減少によって、生態系にどういう影響が出るのかを十分に推定できる状況にありません。
命の水として大切に受け継がれてきた大井川上流部の美しい清流、また世界の宝であるユネスコエコパーク南アルプスの優れた自然環境を、しっかりと保全するのは、県の持つ国際的な責務であります。
JR東海の今回の回答は理解しやすさという点では配慮なさったものの、まだまだ内容はとても十分であると言えるものではありません。今後、中央新幹線環境保全連絡会議の専門部会等におきまして、実際に調査したデータに基づく施工や環境保全等の計画を求めまして、水量、水質の確保と自然環境の保全等について、科学的根拠に基づき粘り強く対話を進めるなど、県民の皆様の不安の払拭に向けて全力で取り組んでまいります。
項 目 2 部局長のマネジメントによる事業見直しの徹底について
答弁者 政策推進担当部長
質問要旨 県が本年度の当初予算編成から導入した、各部局に財源を配分する枠配分方式については、部局長が自らの責任において、現場の抱える課題に対応する予算を調整することが可能となったものと、高く評価する一方、各部局の事業改廃については改善の余地があると考えている。
当初予算の説明では、新規事業や制度の説明が大半で、事業廃止により産み出した人工や予算をどのように新規事業に活用したのかといった、事業見直しについては、ほとんど説明されない。
本年度当初予算の編成方針では、部局長のマネジメントによる徹底的なスクラップアンドビルドにより43億円を捻出することとされていたが、最終的にどのような事業見直しがされたのか見えていない。
部局長が新たな事業を行うためには、何かを削減しなければならないという認識を強く持ち、責任を持って事業の見直しに取り組むことが重要である。また、新規事業とあわせて、見直し内容についても知事のもとで議論が必要と考える。
事業見直しを実効性のあるものとするため、県はどのように取り組むのか所見を伺う。
<答弁内容>
部局長のマネジメントによる事業見直しの徹底についてお答えいたします。
限られた財源、人的資源の中で、新たな事業を立ち上げるためには、既存事業の見直し、スクラップアンドビルドの徹底による資源の再配分が不可欠であり、現場に精通する部局長自らが責任を持って取り組むことで、その実効性は高まるものと考えております。
昨年度、新たに枠配分方式を取り入れ、各部局長のリーダーシップの下、配分された財源を元に、政策評価に基づく事業の見直しに取り組んだところであります。結果としては、実施回数・作成部数の減や事業費の精査など部分的な見直しにとどまることも多く、事業そのものの廃止や縮小など、更なる見直しが必要であると認識しております。
このため、来年度の当初予算編成に向けましては、エビデンスに基づく事業評価を強化することといたします。具体的には、評価の低い政策に関連する事業について、データに基づく現状分析を徹底し、課題解決に直結する効果的な手法を明確にし、部局自らの積極的な事業見直しを促してまいります。
また、事業評価の結果を踏まえ、見直し、廃止、縮小により生み出される人的資源を新たな重点施策の実施に充てるなど、政策調整と予算編成のシステムに人員配分適正化の視点を加え、施策の実効性を更に高めてまいります。
事業見直しを徹底するこれらの取組につきましては、知事戦略会議や政策調整会議など、当初予算編成の過程を通じて検証を行い、その結果について「見える化」を図ることにより、実効性を更に高めてまいります。
以上であります。
項 目 3 消防防災ヘリコプターの活用と安全対策について
答弁者 危機管理監
質問要旨 県の消防防災ヘリコプターは、9月1日からイタリア・レオナルド社製の新機体での運用が始まった。新しい防災ヘリは、機体がこれまでよりも大型化し、エンジン出力も大幅に増大するほか、巡航速度が上がり、航続距離が伸びるため、災害への対応力も向上すると伺っている。今回の機体のグレードアップを、本県の災害対応力の向上にどのように活かしていくのか伺う。
一方、新しい機体の優れた性能や機動力を活かしていくためには、安全体制の向上も欠かせない。過去の相次ぐ事故の教訓を踏まえ、総務省消防庁は、「二人操縦士体制」などを盛り込んだ新たなヘリコプターの運航基準を定め、地方自治体に勧告する方針を固めたと聞いているが、国から示される運航基準などを踏まえ、今後どのように消防防災ヘリコプターの安全対策の向上に取り組むのか、併せて伺う。
<答弁内容>
消防防災ヘリコプターの活用と安全対策についてお答えいたします。
運航を開始した新しいヘリコプターは、旧型機よりも大型化し、航続距離が1.3倍の730kmとなるなど、大幅に性能が向上いたしました。南海トラフ地震などの大規模災害時には、被災者の救助、物資の搬送等におきまして、今まで以上の活躍が期待され、例えば、下田市から静岡市へ被災者を搬送する場合、1日に搬送できる人数が50人から120人程度に大幅に増加いたしました。
また、本県は、浜名湖から伊豆半島まで500kmに及ぶ海岸線や、富士山、南アルプスなどの山岳地帯を有しております。巡航速度が向上し、高高度での活動も可能となりましたので、従来に増して、迅速かつ広範囲での救助活動が展開できるものと考えております。さらに、空中からの消火が効果を発揮する林野火災におきましても、従来の約3倍の水を積載することが可能となり、消火能力が大幅に向上いたしました。
ヘリコプターの安全対策につきましては、総務省消防庁から、「消防防災ヘリコプターの運航に関する基準」が近く勧告されると聞いておりますので、県といたしましては、勧告の内容や国の財政支援措置等を踏まえ、二人操縦士体制の導入など、ヘリコプターの安全対策の充実強化に努めてまいります。
以上であります。
項 目 4 医師不足対策について
(1)医師不足と医学修学研修資金のあり方
答弁者 知事
質問要旨 静岡県は医師不足が深刻であり、県内唯一の医師養成機関である浜松医科大学は掛け替えのない存在である。
県は浜松医科大学に対し、東部地域のみに焦点を当てた医師派遣の要請を行っているが、同医科大学のみで県全域の医療をカバーするのは非現実的であり、医師派遣の要請は、東部地域に拘泥せず柔軟なものとすべきと考えるが、県の所見を伺う。
また、医学修学研修資金の返還免除勤務の算定に際し、浜松医科大学附属病院における勤務期間に相当する期間、東部地域の病院にも勤務することが条件とされていることは大きな問題と考える。浜松医科大学附属病院での勤務期間を他の公的病院と同様に返還免除対象として認定すべきと考えるが、県の所見を伺う。
<答弁内容>
次に、医師不足対策についてのうち、医師不足と医学修学研修資金のあり方についてであります。
本県の医師不足は、県内の医学部入学定員が人口比で全国46位と医師養成数が少ないことが大きな要因であると考えております。そのため、私は医師確保を最重要施策の一つに位置付けてまいりました。そして、平成26年度に本庶佑先生の御協力を得て「ふじのくにバーチャルメディカルカレッジ」を創設いたしました。医学修学研修資金の貸与、あるいは地域枠の設置など、取組をしてまいったところであります。
特に、医学修学研修資金につきましては、これまで累計で1,000名を超える方が利用しており、全国最大規模の実績を誇っております。その結果、今年4月1日現在の県内勤務者は、前年から96人増になり、461人となりました。これは、取組の成果が着実に現れている数字的な表現であります。また、本県の制度は、返還免除のための勤務期間中でも、大学院への進学や海外留学をすることができる猶予期間を設けるなど、利用者のキャリア形成に配慮した、柔軟なものになっております。
さらに、東部地域の医師不足を解消することを目的として、医学修学研修資金利用者が東部地域の公的病院等で勤務した場合には、大学附属病院での勤務期間を返還免除対象とする特例を設けるなど、これまでも制度の見直しを実施してまいりました。
こうした中、昨年度の新専門医制度の開始により、若手医師が自身のキャリア形成に強く関心を抱く傾向が顕著となっております。このため、医学修学研修資金制度につきましても、更に医師のキャリア形成に配慮した内容とすることで医師の県内定着を促進するように、ふじのくに地域医療支援センター理事会等の御意見も伺いながら、制度の見直しを進めております。
具体的に申し上げますと、利用者のキャリア形成を長期にわたり支援することを目的として貸与期間を原則、医学部に在籍する6年間といたします。それとともに、県内での専攻医を確保することを目的として県内大学の附属病院における勤務を、他の公的医療機関での勤務と同様に、返還免除勤務として算定するなど、改正を行う方針であります。また、浜松医科大学への医師派遣要請の在り方につきましては、これらの改正に併せて見直しを行い、大学と連携して医師不足地域での医療の確保に努めてまいります。
私どもといたしましては、より多くの医師を確保するとともに、効果的な地域偏在の解消を行い、医学修学研修資金の貸与をはじめ、地域枠の更なる増設等、各種の取組を全方位で進めまして、県民の皆様が安心して住み続けることのできる医療提供体制を構築してまいります。
項 目 4 医師不足対策について
(2)地域枠医師
答弁者 健康福祉部長
質問要旨 県は県外大学への地域枠の設置を進めており、今後、数年内に卒業生が県内病院に勤務する予定である。地域枠を設置した都内や神奈川県内の大学は県東部地域に近く、その機関病院が県内病院と連携し、臨床研修や専門研修を通じ、医師を派遣することが最も実現可能性が高い医師確保の方策と考えるが、県の所見を伺う。
<答弁内容>
医師不足対策についてのうち、地域枠医師についてお答えいたします。
地域枠は、医学修学研修資金の貸与を受け、卒業後には都道府県内の地域医療に従事することを条件とする入学定員枠であり、本県は、県外からの医師の確保を目的として、県外大学への設置を積極的に進めてまいりました。その結果、本県が現在、県外大学に設置している地域枠は7大学34人に上り、全国最大規模となっております。
議員御指摘のとおり、東部地域におきまして、県外の地域枠設置大学から研修医や専攻医を継続して確保することは、医師不足を解消するための有効な手段の一つであると認識しております。
このため、県といたしましては、東部地域の各市町の協力も得ながら、公的病院等と本県の地域枠設置大学との専門研修プログラムにおける連携や、地域枠学生の県内実習の受入れなど、両者のマッチングの推進等を通じた関係強化を図ることで、県東部に勤務する医師の確保、定着に努めてまいります。
項 目 4 医師不足対策について
(3)浜松医科大学の医師養成機関としての機能の活用
答弁者 健康福祉部長
質問要旨 浜松医科大学は、多くの地域医療に貢献する優れた医師を輩出してきた。
また、同大学附属病院の医師は、臨床研修医や専攻医への教育だけでなく、基幹病院や休日夜間救急センターへの支援などにも大きく寄与している。
このような浜松医科大学及び同大学附属病院が有する医師養成機関としての機能を県が行う事業に積極的に活用していくことが必要であると考える。
そこで、浜松医科大学の医師養成機関としての機能を今後、どのように活用していくのか、県の考えを伺う。
<答弁内容>
次に、浜松医科大学の医師養成機関としての機能の活用についてであります。
浜松医科大学及び同大学附属病院には、本県唯一の医師養成機関として、県内で活躍する多くの医師の養成や県内病院への医師派遣、高度医療の提供など、本県の地域医療の推進と医療の質の向上に多大な貢献を頂いております。
特に、保健医療計画において重点的に取り組むこととしている周産期、家庭医療、児童精神等の各分野につきましては、浜松医科大学にそれぞれ寄附講座を設置し、専門性の高い医師の養成に連携して取り組んでおります。また、医師養成機関としての機能を活用して女性医師支援や精神疾患に係る連携体制整備等の取組を着実に推進しております。
さらに、昨年度の医療法等の一部改正により、地域枠医師等を対象とする「キャリア形成プログラム」の作成が都道府県に義務付けられております。浜松医科大学の協力の下、キャリア形成の基本プログラムとして3つのコースを示し、これを基に県内21の基幹病院が計175の個別プログラムを作成しております。
今後も浜松医科大学と連携して、一人ひとりのニーズに応じた専門性の高い研修プログラムの提供等、医師にとって魅力ある制度運用をすることにより、県内への更なる定着を推進してまいります。
県といたしましては、現在、策定中である医師確保計画につきまして、引き続き浜松医科大学をはじめ関係者の皆様から広く御意見を伺い、施策に反映していくとともに、今後も、浜松医科大学が有する医師養成機関としての機能を最大限に活用させていただくことにより、県民の皆様が安心して暮らすことができる医療提供体制の構築に努めてまいります。
項 目 5 聖隷三方原病院ドクターヘリ格納庫について
答弁者 健康福祉部長
質問要旨 現在、聖隷三方原病院が運航しているドクターヘリには、格納庫がない。
格納庫ができれば、日常の点検が効率的に実施でき、また、風雨による機体の劣化を防ぐこともできる。
格納庫の早期整備が必要と考えているが、進捗状況について答弁を求める。
<答弁内容>
次に、聖隷三方原病院ドクターヘリ格納庫についてであります。
県では、全国に先駆け、平成16年10月にドクターヘリ2機体制を構築し、県内全域を出動範囲とした救急医療体制を確保しております。本年5月には2機合計の累計出動件数が全国で初めて2万回を超えるなど、救急医療やへき地医療に大きな成果を上げているほか、大規模災害が発生した際の医療救護活動においても重要な役割を担っております。
こうしたドクターヘリの活躍を支えるため、平成28年度には、県と伊豆の国市をはじめとする関係21市町が協力して、東部ドクターヘリを運航する順天堂大学医学部附属静岡病院の格納庫の整備を支援し、機体管理の環境を整えることで、今まで以上に、安全かつ安定的な運航の確保を図っております。
西部ドクターヘリを運航する聖隷三方原病院におきましては、これまで、県や浜松市も協力して格納庫の候補地を探しておりましたが、今年になり病院近くに候補地が見つかったため、格納庫の整備を進めたいとの報告を受けたところであります。
このため、当該土地の整備に必要な許認可等の手続きを経て、整備計画が具体化した際には、病院が早期に格納庫を整備できるよう、国や関係市町と連携し、支援していきたいと考えております。
県といたしましては、今後も、ドクターヘリの運航を支援することにより、「命を守る」ための救急医療体制の確保を図り、県民の皆様が住み慣れた地域で、安心して生活できる「ふじのくにづくり」を目指してまいります。
以上であります。
項 目 6 水産資源の保全について
(1)水産資源と魚病のスペシャリストの育成
答弁者 農林水産担当部長
質問要旨 昨今、浜名湖のアサリや駿河湾のサクラエビなど水産資源の枯渇が問題になっており、対策を考えるには多くの経験と知識が必要だが、県の担当職員が定期的に変わってしまうため経験と知識の蓄積ができていない。対策には各漁業者との信頼関係が必要だが、それも叶わない。
また、県内には鰻をはじめとした養殖業がさかんであるが、魚病への対策を考える上でも、資源と同じく、人の課題がある。
横に広い静岡県なので、例えば東部の沼津と浜名湖にそのエリア専門の職員を配置すべきと考えるが、県の所見を伺う。
<答弁内容>
水産資源の保全についてのうち、水産資源と魚病のスペシャリストの育成についてお答えいたします。
県の水産に関わる技術職員の業務内容は、資源調査や増養殖のほか、水産加工、普及指導と多岐にわたっており、魚の種類別にも深い専門知識と経験が必要となります。
このため、浜名湖のウナギ、アサリや、駿河湾のサクラエビ、伊豆東岸のキンメダイなど、本県の重要な地域魚種に関する研究や指導を主に担当する職員については、必要に応じて、通常の異動サイクルである3年から5年よりも長い期間、場合によっては10年以上の長期間にわたり、同一分野の業務を担当させることなどにより専門性を高め、漁業者から信頼をいただけるよう努めているところであります。
また、魚病対策に関しましては、農林水産省から受託した日本水産資源保護協会が、水産防疫及び養殖衛生管理に関する専門的知識と技術を有する者として認定します魚類防疫士という資格について、計画的な取得を進めております。
現在、9名の職員がこの資格を有しており、東部の富士養鱒場や西部の浜名湖分場にこれらの職員を配置しまして、アジやニジマス、ウナギ、アユなどの養殖について、魚病診断や巡回指導、講習会の開催など、魚病対策の的確な推進を図っているところであります。
県といたしましては、職員本人の希望や適性を踏まえつつ、県内各地域の水産資源対策や魚病に関する専門性の確保にも十分留意しながら、これからもスペシャリストの育成に努めてまいります。
項 目 6 水産資源の保全について
(2)県内水産資源の防疫体制
答弁者 農林水産担当部長
質問要旨 近年水揚げ日本一を誇る愛知県のアサリ漁が、深刻な不漁に陥っている。主な漁場の三河湾でカイヤドリウミグモという寄生生物が大量発生していることが減少の大きな要因と聞く。現在浜名湖では確認できていないが、浜名湖に来れば大きな影響をうけることは予想できる。また、パーキンサス属原虫によるアサリの漁獲減少もあると聞く。
そこで、県として、アサリをはじめとした水産資源の防疫体制の強化にどのように取り組むのか、県の所見を伺う。
<答弁内容>
次に、県内水産資源の防疫体制についてであります。
アサリや養殖魚など、外部からの種苗導入により増殖可能な水産資源について防疫対策を実施するに当たりましては、本県の水産資源に損害を及ぼすおそれのある新たな魚病の持ち込みを防止することが、最も重要であると考えております。
国では、卵や稚魚が地球規模で取引されているサケ・マス類など、海外から新たに魚病が侵入する危険性が高い養殖魚種につきまして、魚病のまん延防止を目的として、水産防疫対策要綱を定めております。本県でも、この要綱に沿って、海外から魚介類の卵や稚魚を輸入する際には、関係する事業者に対しまして、一定期間隔離して飼育し、異常のないことを確認するよう指導するなど、新たな魚病の持ち込みを防ぐため、その対策に努めているところであります。
また、近年不漁が深刻化している浜名湖のアサリにつきましては、他産地の稚貝を導入して増殖を図りたい旨の声を聞くこともありますが、議員御指摘のような課題がありますことから、その危険性について水産技術研究所などが漁業関係者に周知を図っているところであり、現在、他産地からの稚貝の導入は行われておりません。
県といたしましては、引き続き、関係者とも十分連携を図りながら、水産資源の防疫の確保に万全を期してまいります。
項 目 7 荒廃農地対策について
答弁者 農林水産担当部長
質問要旨 湖西市で生産されている、花き類や野菜類等は、20年もの歳月をかけて農業生産基盤の整備に取り組んできた賜物である。
しかしながら、社会情勢の変化に伴い、農業者の高齢化や担い手不足が進行し、基盤整備事業が実施された地区でも荒廃農地の発生が懸念される。
こうした中で、近年、市内の規模拡大意欲の高い若手農家の中から、荒廃農地を再生して積極的に活用していきたいという声が上がっており、新たな農地を求める農業者に対し、支援をしていくことが地域農業のさらなる活性化にとって重要と考える。
そこで、荒廃農地を拡大意欲のある農家にどのように結び付けていくのか、県の取組を伺う。
<答弁内容>
次に、荒廃農地対策についてであります。
農地は、農業生産活動を通じて食料を安定的に供給する場であるとともに、適切な管理により地域の環境や景観の保全にも寄与するものでありますことから、後継者不足により荒廃化が懸念される優良農地を意欲ある担い手が耕作し、将来にわたって有効に活用していくことが重要であると認識しております。
しかしながら、規模拡大意欲の高い若手農家などが農地を借りたくても所有者の同意を得られずに借りることができない事例や、農地を貸したくても借り手が見つからないまま荒廃化する事例も見受けられます。
こうしたミスマッチを解消するためには、まずは集落や土地改良区等の単位で、5年後、10年後の地域農業を誰が担い、どのように農地を集積するのかを農業者同士で話し合い、その結果を取りまとめた「人・農地プラン」を作成し、それに基づき農地中間管理事業による農地の貸し借りを進めていくことが必要であります。
これまでにも、磐田市西貝地区におきまして、農林事務所の職員が市やJA職員とともに地区の話し合いに参画し、担い手とのマッチングを提案するなどの検討を重ねて地域の将来像をまとめ、これを基に農地の貸し手と借り手を結び付けた実績がありますことから、県では、関係機関と連携したこのような取組を他市町にも広げてまいります。
あわせて、担い手が農地中間管理事業により借り受けた荒廃農地につきましては、立木の除去や整地等を農業者の負担なしで行う事業を活用して再生を進めてまいります。
県といたしましては、今後とも、市町、JAなどとの連携の下、荒廃農地等を活用して、意欲ある担い手農家の経営が発展するよう支援し、地域農業の活性化につなげてまいります。
以上であります。
項 目 8 水道事業の広域化について
答弁者 くらし・環境部長
質問要旨 料金収入の減少や施設の更新需要の増大は、県内の水道事業が直面しており、経営基盤の強化は共通の課題であり、特に、中小規模の公営企業では、職員数が少ないこともあって、問題がより深刻であり、現在の経営形態を前提とした経営改革だけでは、将来にわたる住民サービスを確保することが困難となり、持続できない可能性がある。
将来にわたって安定的にサービスを確保していくためには、現在の経営形態のあり方自体を見直し、広域化をはじめとした抜本的な改革が必要である。
現在、県においても行政経営研究会を中心に取り組んでいるが、さらに広域化の実現に向け、取組を加速させる必要があると考えている。
会派としても大きな課題だと認識しており、私も2年前に、いち早く水道の広域化を実現した香川県の水道事業広域化政策部水資源対策課水道広域化推進室に話を伺ったところ、広域化を目指す上で難航した点は、1水道料金の平準化、2施設整備水準の平準化、3職員の給与体系の平準化、4水道事業者の入札制度の設計の主に4点とのことであった。
そこで、県として水道事業の広域化をどのように進めていくのか所見を伺う。
<答弁内容>
水道事業の広域化についてお答えいたします。
将来にわたり安全で安定的な水の供給を継続するためには、水道事業の経営基盤強化が重要でありますことから、県では、水道事業者である市町ごとの経営課題を把握した上で、広域化を推進することとしており、連携の対象区域や、その特性に応じた連携策を検討しております。
本年度は、全市町を対象に、施設の更新計画や財政計画から成る「経営戦略」等を基に、個別のヒアリングを実施するなど、各市町の経営状況の現状や課題の把握に努めているところであります。
あわせて、市町に広域化の効果を理解していただくため、自己水源に恵まれず、大井川広域水道企業団等からの給水に頼る、掛川市、菊川市、牧之原市、御前崎市で構成される東遠地域をモデルに、申請受付業務や施設の運転及び保守管理業務を共同発注した場合のシミュレーションを行っております。
県といたしましては、今後、各市町の水道事業の経営課題を的確に把握し、シミュレーションによるコスト削減等の効果を共有しながら、市町と話し合いを重ね、まずは、広域化に向けた第一歩となる、本県の「水道広域化推進プラン」を策定してまいります。
<再質問>
香川県は、県全域を1つとして水道の広域化を実現した。静岡県は、県域が横に広いので、ある程度何個かのエリアに分けて広域化することも一つの案なのかと思っているが、そのエリア分けという考えに対して、今の見解を伺う。
<答弁内容【再質問】(答弁者:くらし・環境部長)>
水道事業の広域化の再質問についてお答えいたします。
広域化のエリアについてどのように考えるか、という御質問でありますが、香川県は、議員から御紹介がありましたとおり、全県で一つ、一本化で広域化したという事実がございますが、静岡県は面積も広く、横にも長く、各市町の置かれております水道の供給元というのが、色々異なっております。
項 目 9 二地域居住の推進について
答弁者 くらし・環境部長
質問要旨 県では、様々な移住政策を推進し、成果も上がっていると認識しているが、IT技術が進化している現在、二地域居住を進め、関係人口を増やすことが本県の発展につながると考える。
具体的には、IT企業の従業員が東京とサテライトオフィスのある浜名湖の二地域に居住する、或いは、ライフスタイルの充実を図りたい会社員が平日は東京、週末は伊東に二地域居住することも考えられる。
他県でも、民間企業と協力して、トライアル移住・二地域居住を推進するプロジェクトなどの取り組みが始められている。
本県でも、関係人口の増加に向けて、二地域居住の取り組みを進めていく必要があると思うが、県の所見を伺う。
<答弁内容>
次に、二地域居住の推進についてであります。
二地域居住は、都会に暮らす人が、週末や一年のうちの一定期間を地方で暮らすなどのライフスタイルの一つであり、観光客などの交流人口と定住人口の中間に位置する関係人口に該当し、移住にもつながるものと考えております。
このため、移住セミナー等におきまして、東京圏で暮らす方を対象に、週末は自然豊かな本県で、家庭菜園やマリンレジャー、温泉などを楽しみながら過ごす暮らし方の提案を行っております。
また、二地域居住にもつながるサテライトオフィスの誘致につきましては、県内市町と連携して企業訪問等に取り組んでおり、川根本町や静岡市などで実績を上げております。さらに今年度、AI、ICT人材を本県に呼び込むため、新たに事業所を設置するICT関連企業を対象とした支援制度を創設したところであります。
県といたしましては、こうした取組に加え、移住・定住情報サイトで地域イベントや地域おこし活動への参画の機会をお知らせするほか、市町と連携して地元の方との交流や静岡ならではの暮らし方を体験できるツアーを開催するなど、二地域居住を含む関係人口の拡大に取り組んでまいります。
以上であります。
項 目 10 富士山保全協力金の義務化について
答弁者 文化・観光部長
質問要旨 平成26年度から任意での協力金制度を導入しているが、その制度を検討した利用者負担専門委員会でも、全員からもらうべきなので強制徴収という意見と、世界文化遺産に信仰の山として登録されたことから強制徴収はふさわしくないという意見があり、義務化については賛否両論があった。
海外の国立公園では、相応の入園料を取る場合が多くあり、ニュージーランドのフィヨルドランド国立公園では、徹底した観光客の総量規制が実施されている。
富士山を守るためには、富士山保全協力金を義務化するべきと考えるが、県の所見を伺う。
<答弁内容>
富士山保全協力金の義務化についてお答えいたします。
平成26年度から導入した富士山保全協力金につきましては、昨年度、有識者による利用者負担専門委員会において、これまでの検証を行い、制度の定着は認められたものの、負担の公平性や徴収費用が高額といった課題が指摘されたところであります。また、地元住民や山小屋関係者等による富士山世界文化遺産協議会作業部会では、負担の義務化から中止までの様々な御意見を頂いております。
負担の義務化につきましては、賛否両論があることに加え、全ての来訪者から確実に徴収する方法や、徴収の低コスト化などに課題があり、すぐに結論が出るものではないことから、当面は任意の協力金制度を継続し、協力率の向上に努めてまいります。
静岡、山梨両県では、本年度から対象者を従来の「五合目から山頂を目指す登山者」から「五合目から先に立ち入る来訪者」に拡大するとともに、協力金使途につきましても、様々な登山者の要望に応えることができるよう制度の見直しを行ったところであります。今後、今年度の協力金の納付実績等を、再度、利用者負担専門委員会で検証するとともに、専門委員会委員によるワーキンググループで、義務化を含めた制度改善の可能性について課題の整理を行ってまいります。
保全協力金は、富士山を後世に継承するための貴重な財源であり、登山者の保全意識を高める効果もあります。今後とも、富士山の保全にとって最適な利用者負担制度の確立に向けて、国、山梨県、地元関係者等とも十分調整しながら検討を進めてまいります。
以上であります。
項 目 11 地域交通の充実について
答弁者 知事
質問要旨 昨今、高齢者の運転による重大な自動車事故が各地で頻発しており、また、車が運転できない県民からは買い物や通院するための交通手段がないとの声を多く聞く。例えば、私の地元湖西市白須賀地区においては、近くのコンビニに片道30分かけて買い物に行く高齢者の方がいる。また、高齢者のみならず、浜松駅まで通学している女学生が部活動で帰宅が遅くなった際、家庭の事情により車で駅まで迎えに来てもらえないため、暗い夜道を数十分自転車で走らなければいけないような状況もある。このような状況は私の地元だけの話ではないと思う。早急な課題解決が望まれ、県としても地域交通の充実についてさらなる支援が必要と考えている。
どのような手段で課題解決をするのかに対しては、MaaSと切っても切り離せない自動運転を見越したデマンド型乗り合いタクシーやバスの運用に対しては、県独自の施策を行っていくべきと考える。
そこで、県は地域交通の充実に向け、どのように取り組んでいくのか県としての所見を伺う。
<答弁内容>
地域交通のサービスの充実についての御質問についてお答えいたします。
近年、「人生100年」と言われるようになりました。全ての人が年齢相応に元気に活躍し、安心して暮らすことのできる社会が求められております。特に、高齢者の方々がなどが、豊かな生活を送るためには、移動手段となる各地域の公共交通の充実が必要不可欠であります。
県内では、路線バスや、市町で行う自主運行バス、デマンド型乗合タクシーなど、それぞれの地域の実情に応じた取組がなされております。県では、これら事業に対し経費の助成などを実施しているところです。特にデマンド型乗合タクシーに関しましては、県内14の市町で実施されており、今後ともその取組が増加していくものと考えております。
こうした中、最先端通信技術を活用した公共交通の実用化に向けた取組を進めていくことが重要です。特に、注目を集めているのが御指摘のMaaS、MaaSというのは、モビリティ・アズ・ア・サービスの頭文字をとったもので、移動サービスのことですが、このMaaSにつきましては、鉄道やバス、タクシーなど複数の交通手段の検索、予約、決済をスマートフォンなどで一括して行うことが可能となります。さらに将来は、過疎地域での小型モビリティの活用や都市部でのEVバスの運行など、自動運転の導入も含め、様々なニーズに応じたサービスの展開が期待されます。
県では、このに関する取組の一環として、今年の4月から、東急やJR東日本等の関係機関と共に、市町を跨いだ広域な範囲における試みとしては全国初となる観光型の実証実験を伊豆地域で実施したところであります。この実験では、下田市中心部における移動手段としてデマンド型乗合タクシーを運行し、観光客を中心に御利用いただきました。
さらにこの12月からは、実証実験の運行エリアに、病院やスーパーマーケットなどの住民の日常生活に必要な施設への運行を拡大いたします。デマンド型乗合タクシーによる、新たな公共交通としての可能性を検証するとともに、併せて、特定区間におきましては自動運転車両の走行実験も実施することとしております。
県といたしましては、今後とも新たな交通サービスに関する実験を進め、これからの時代に対応した、県民の誰もが利用しやすい公共交通となるよう積極的に取り組んでまいります。
以上であります。
項 目 12 ICT教育の推進について
答弁者 教育長
質問要旨 県教育委員会では、本年7月、学習指導要領改訂への対応や、Society5.0に向けた学校の在り方を検討するために、「先端技術を活用した教育専門部会」を設置した。
各市町教育委員会では、2020年度からのプログラミング教育の必修化に向けて準備が進んでおり、袋井市の小学校では、エドテックを活用し、子供たち一人一人の学習進度に応じた学習を進める「アダプティブラーニング」を実施するなど先進的な取組も始まっている。しかし、世界を見れば、日本の取組は遅れているのが現状である。
本県におけるICT教育の課題としては、ICT機器の整備と併せて、学校におけるプログラミング教育やICT教育を推進する人材を育成することであり、特に教員のレベルアップには外部人材を含めた対応が必要と考える。
そこで、「先端技術を活用した教育専門部会」における検討内容も含め、ICT教育の課題への対応について、県の所見を伺う。
<答弁内容>
ICT教育の推進についてお答えいたします。
ICT教育の基礎となる機器等の整備につきましては、令和3年度中を目途に、全ての県立学校でプロジェクタ、タブレット等の導入を進めております。しかし、小中学校を含めた県全体の教育用コンピュータの整備状況は、全国平均をやや下回っており、引き続き、市町に強く働き掛け、整備の促進を図っていくこととしております。
また、ICT教育を充実させるためには、議員御指摘のとおり、機器等の整備と併せ、先端技術を有効に活用した授業を実践できるよう、教員の資質・能力を向上させることが極めて重要であります。
このため、県教育委員会では、今年度、新たに小中学校の教員向けにプログラミング教育の授業に関する研修を実施するとともに、多くの教員が受講できるよう、研究内容をeラーニングにより配信しております。また、本年8月には、情報化推進ワークショップを開催し、プログラミング授業の演習を行うとともに、AIを活用した授業や民間企業との連携によるタブレット学習など、先進事例について情報共有を図ったところであります。
さらに、「先端技術を活用した教育専門部会」では、金田(かなだ)ICT戦略顧問やマイクロソフト社などの参画を得て、学校だけではなく家庭での児童生徒個々の学習内容を蓄積できるスタディ・ログや過疎地の学校と大学等を結ぶ遠隔教育など、先端技術の活用について検討し、教員の情報活用能力の更なる向上を図ってまいります。
今後は、将来を担う子供たちが、Society5.0の未来社会において活躍できるよう、専門部会における検討を踏まえ、大学、民間企業と連携し、AI等の先端技術を効果的に活用した新時代の学校を実現するため、ICT教育環境の整備や教育内容の充実に積極的に取り組んでまいります。
項 目 13 夜間中学の設置についてて
答弁者 教育長
質問要旨 夜間中学は、義務教育を修了しないまま学齢を経過した者や、不登校など様々な事情から実質的に十分な教育を受けられないまま学校の配慮等により中学校を卒業した者、9年間の普通教育を十分に受けられないまま学齢を超過した外国籍の者に対して、教育を受ける機会を保障するための重要な役割を果たしている。
文部科学省では、全ての都道府県に少なくとも一つの夜間中学の設置を求めており、現在、本県には夜間中学は設置されていないが、本県においても、外国籍の人や不登校の児童生徒が増加していることから、早急な対応が必要だと考える。
夜間中学設置については、平成31年2月県議会において、教育長から「夜間中学の果たす役割を十分に認識し、市町教育委員会と連携して、県内に住む全ての人々に義務教育の機会を提供することができるよう、積極的に取り組む。」との答弁があったが、その後の進捗状況と、今後の具体的な取組について伺う。
<答弁内容>
次に、夜間中学の設置についてであります。
本県に住む外国人は9万人を超え、今後も更に増加することが見込まれております。また、昨年度、外国籍や引きこもりの傾向にある人を対象に行った調査では、学び直しを希望するとの回答が約8割ありましたことから、このような人達に教育の機会を提供するため、夜間中学を設置する必要があると考えております。
県教育委員会では、本年7月、各市町教育委員会を対象に「夜間中学研修会」を開催し、本年度の県内ニーズ調査の結果や全国での設置状況に関する情報等を提供し、具体的な検討を依頼したところであります。また、8月に行われた文部科学省の「夜間中学日本語指導研修会」に担当職員を派遣するとともに、先行して設置している他県の夜間中学を視察し、設置形態、入学資格、募集人員等のほか、設置に向けた課題について把握に努めております。
具体的には、対象者が県内の広域に存在し、さらに、入学希望者の学習レベルが様々であり、ニーズも多様でありますことから、設置場所や教育課程の内容、教員等の人的配置、募集方法などが課題となっております。
現在、各市町教育委員会に対して意向調査を行っており、今後は、設置を前向きに考えている市町とともに協議会を立ち上げ、具体的な協議を行っていきたいと考えております。
県教育委員会といたしましては、市町教育委員会と連携し、外国籍、日本籍の誰もが、教育の機会を得られるよう、夜間中学の設置に向けて積極的に取り組んでまいります。
項 目 14 放課後の子供の過ごし方について
答弁者 教育部長
質問要旨 国が策定した「新・放課後子ども総合プラン」は、2023年度(令和5年度)末までに全国の全ての小学校区で、放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的に又は連携して実施し、そのうち一体型のものを1万箇所以上にすることを目標として掲げている。放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的型又は連携型が推進される一方で、その目的がである「すべての児童が放課後子供教室の活動プログラムの参加」という点で効果が十分あらわれていないのではないかと感じる。
今後は、子供たちが興味を持てるメニューを増やすなど放課後子供教室の充実を図り、そのうえで放課後児童クラブとの連携を進める必要があると考える。そこで、県は子供たちの放課後の過ごし方の課題をどのように認識し、どのような取り組みを今後されるのか県の所見を伺う。
<答弁内容>
放課後の子供の過ごし方についてお答えいたします。
昨年度の全国学力・学習状況調査のうち、小学校6年生の放課後の過ごし方についての回答では、「家でテレビやビデオを見たり、ゲームやインターネットをしている」が最も多く、次いで「友達と遊んでいる」「家で勉強や読書をしている」などとなっております。
夫婦のいる一般世帯では、共働き世帯が5割以上を占めるまで増加しており、国が策定した「新・放課後子ども総合プラン」で示されたように、放課後児童クラブと放課後子供教室により、子供たちが、放課後、安全・安心に過ごしながら、多様な学習や体験・交流活動の機会を持つことは大変重要であると考えております。
このうち、放課後子供教室は、本年度は218か所で実施されており、10年前の倍以上となっております。学校の余裕教室や公民館等で、地域住民等の協力を得て、英語科の教科に係る学習支援や料理、工作、農業、スポーツ等の体験活動を実施しており、子供たちの社会性や規範意識、自主性、コミュニケーション能力の向上等の効果が見られております。
しかしながら、放課後子供教室の活動プログラムに参加している放課後児童クラブは3割程度にとどまっており、連携を進めていくためには、双方の活動への理解と、放課後子供教室において、子供の興味・関心を引き付けるプログラムの内容を充実させることが重要であります。
このため、運営の要となる地域コーディネーターを養成する講座や、指導者等を対象とした研修会の場で、県内外の先駆的・先進的な活動事例や放課後児童クラブとの円滑な連携の事例等を紹介するとともに、人材養成やプログラム開発能力の向上を図ってまいります。
県教育委員会といたしましては、子供たちが放課後も生き生きと過ごせるよう、健康福祉部や市町教育委員会と連携し、社会総掛かりでの子育て支援、教育の充実に努めてまいります。
項 目 15 学校における防犯カメラの設置について
答弁者 教育部長
質問要旨 近年、学校に通う子供が狙われる事件が多発している。登下校の全てを見守ることは極めて困難であり、子どもたちをどう守るかが改めて問われているが、ボランティアやPTAによる通学路の見守り活動のようなソフト対策も大変重要だが、防犯カメラの設置等のハード対策も重要である。
現在、県内500校の小学校のうち、175校が防犯カメラを設置しており、今後、新たに設置する予定の学校もある。企業でも、ある飲料販売メーカーが協力企業に自販機を設置し、その収益で学校に防犯カメラを設置する取り組みをしている例もあり、防犯カメラは安全対策に有効であると考える。
県としても特に小中学校と特別支援学校の防犯カメラの設置を前向きに取り組んでいただきたいが、子供の安全を守るための学校における防犯カメラの設置についてどのように考えているのか県の所見を伺う。
<答弁内容>
次に、学校における防犯カメラの設置についてであります。
学校の防犯カメラにつきましては、文部科学省が定める校種ごとの「施設整備指針」におきまして、不審者の侵入防止や児童生徒の安心感を醸成するなどの設置目的を明確にした上で、見通しが困難な場所や死角となる門や建物の出入口付近などに設置することが有効であるとされております。
県内の小中学校では、本年7月末現在で、約4割の学校に防犯カメラが設置されており、熱海市や清水町、藤枝市など8市町では、全ての小中学校に設置されております。設置済の学校からは、「抑止力が高まり犯罪防止に役立っている」「安心感が増した」などの意見が聞かれております。
また、特別支援学校では、本年6月に策定した「子どもの安全確保緊急対策アクション」に基づき、全てのスクールバスにドライブレコーダーを設置するとともに、防犯用品として催涙スプレーや防犯ブザーを備えたほか、一部の学校において防犯カメラを導入するなど、安全対策を強化したところであります。
県教育委員会といたしましては、学校安全担当者を対象とした研修会等の場で、防犯カメラの設置状況や防犯用品の活用事例など、市町や学校の取組について情報提供しながら対策の充実を働き掛けるとともに、警察等の関係機関と連携し、地域や学校の実情に応じた効果的な安全対策が行なわれるよう取り組んでまいります。
以上であります。
項 目 16 サイバー犯罪の現状と県警察における体制及び犯罪被害防止対策について
答弁者 警察本部長
質問要旨 ―
<答弁内容>
サイバー犯罪の現状と県警察における体制及び犯罪防止対策についてお答えします。
情報通信技術の発展により、インターネットは日常生活に欠かせないものとなっております。
全国的に、刑法犯検挙件数が減少傾向にある一方で、サイバー犯罪の検挙件数は増加傾向にあり、今後キャッシュレス決済やIoTの更なる普及とともに、サイバー犯罪はさらに増加することが懸念されます。
本県におけるサイバー犯罪の検挙件数は、ここ数年、150件前後で推移しており、本年8月末では、昨年同期比+5件の94件を検挙しております。罪種としては、インターネットを悪用した児童買春・児童ポルノ禁止法違反、わいせつ物頒布が多く、コンピューターを対象とした不正アクセス事件も5件検挙しております。
また、相談件数につきましては、本年8月末現在922件で、昨年同期比-169件となっております。
次にサイバー犯罪に対する体制についてであります。
本県警察では、サイバー犯罪対策課を中心に専門的な知識を持った警察官を配置して、不正アクセスやコンピューターウイルス犯罪について捜査に当たらせており、また、サイバー犯罪対策課以外の課においても、捜査員を研修に参加させるなどして、サイバー犯罪捜査能力の向上に努めております。
最後にサイバー犯罪被害防止対策についてであります。
サイバー犯罪は、ひとたび被害が発生すれば犯人の特定や被害の回復に相当な困難を伴いますことから、現実空間と同様に被害に遭わないことが大切です。
最近では、大手企業の決済システムへの不正アクセスによる金銭的被害が問題となっておりますが、これらはいずれもシステム自体に脆弱性があったものと報道されております。
県警察といたしましては、こうした事態に対処するため、企業を対象に、民間事業者と連携したサイバーセキュリティセミナーを開催し、被害に遭わないためのセキュリティ対策機材の導入等、企業におけるセキュリティ対策の強化を呼びかけております。
また、一般利用者には、学校や各種関係団体を対象としたサイバーセキュリティカレッジにおいて、被害防止対策についての情報提供をするなど、様々な機会に周知活動を行って被害防止に努めております。
以上であります。